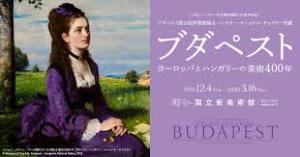2020年 04月8日 - 日常
仏教での「花まつり」とは、〈お釈迦さまのご生誕をお祝いする日〉のことです。お釈迦さまが誕生したのは、今から約2500年前の4月8日と言われていますから、毎年4月8日の前後には、宗派に関係なく全国の寺院や地域をあげてお祝いしています。花まつりは、お釈迦さまが生まれた時に龍が天から飛んできて、香湯をそそいだといういわれがあることから、灌仏会とも言われています。お釈迦さまは、釈迦族の王シュッドーダナとその妃マーヤーの長子としてルンビニー園で生まれました。伝説では、お釈迦さまは、お生まれになってすぐに7歩進み、右手で天を、左手で地を指差し「天上天下 唯我独尊(てんじょうてんげ ゆいがどくそん)」と宣言されたといわれています(『長阿含経』)。

「天上天下唯我独尊」とは、この世に個として存在する「我」より尊い存在はないという意味で、人間の尊厳を表した言葉です。「我」は釈迦のことではなく、この世に生まれた個人の誰もが、その存在が尊いものだという意味です。また「独尊」には、唯一の尊い使命という解釈があり、お釈迦さまが、この世にあらわれた目的は、一切の人を救うことだとする説もあります。
思いを巡らせれば、私どもは皆、お釈迦さまと同じように、誰にもかわることの出来ない、かけがえのない「いのち」を生きていることに気づくことでしょう。人類が誕生して以来、数え切れないほどの人びとが生き、また現在、数10億の人びとが共に存在しているなかで、誰1人として「わたし」と同じように生き、悩み、考え、行動する人はいないのです。4月8日は、お釈迦さまの誕生をお祝いすると同時に、それぞれの「かけがえのない命の尊さ」に眼を向け、正しく生きることをお誓いする日にしたいものです。
花まつりに欠かせない「甘茶」は、ガクアジサイの変種でユキノシタ科の植物「アマチャ」の若葉を煎じた飲み物です。甘茶は生薬としても知られるように、無病息災の効験があるとして重宝されています。
また、奈良時代から江戸時代ごろまでは、甘茶ではなく香水(こうずい)という水が使われていたようです。
1日の感染者数500人超え、最多更新。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 04月7日 - 日常
毎日読んでくれている友人から「昨日はブログどうしたの?」という連絡が来ました。そこで今になって確かめてみたら、昨日アップしたつもりの記事が公開されていなくてガッカリしています。それも、下書きにも残っていません。昨日の記事は、石破茂衆議院議員が春を迎えるこの時季に聴きたい楽曲についてのコメントに対して、共感するものがあり、ユーミンや南沙織、柏原芳恵、キャンディーズ・・・を追いかけてみました。ザンネン。

今月も皆大好き、満月の日がやってまいりました。2020年4月7日深夜から8日未明にかけて、「ピンクムーン」と呼ばれる4月の満月が夜空を照らします。ネイティブアメリカンの間で4月の満月は「ピンクムーン」と呼ばれており、6月の「ストロベリームーン」と並んで人気な満月です。実際に月がピンクになる訳ではありませんが、冬が過ぎ暖かい4月には綺麗な花々が咲くように、花の色にちなんで4月の満月に付けたと言われています。この満月を見た人は「恋愛運にご利益がある」「幸せをもたらしてくれる」というロマンチックな噂があるそうです。
今夜は北海道から九州にかけて広い範囲で晴れる予報で、夜空を眺めるのにはピッタリな天気になるでしょう。
空気も乾燥しているため、より一層輝きを増した月を見ることができそうです。月明りを上手に避けて、周りの星を観察するのも良いですね。
コロナウイルス感染拡大防止で自宅待機が要請されています。時間がある夜には、ゆったりと夜空を眺めてみるのも良いのではないでしょうか。暗いニュースばかりの毎日ですが、こんな時は「おうち時間」を有意義に使いましょう!
首相が緊急事態宣言、7都府県で5/6まで。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 04月5日 - 日常
豆腐を作るときに出るしぼりかすである「おから」、私はけっこう好きです。野菜と一緒に煮ておかずにするのは定番ですが、ケーキやクッキーに使ったり、ハンバーグのたねに加えたり、今では様々な使い方がされていますね。そんなおからですが、「卯の花」とも呼ぶこともあります。和食の世界では、本来の食材の呼び名ではなく、別の名前で呼ぶケースがあります。そのひとつがおからですね。おからの〈から〉が〈からっぽ〉に繋がるのを嫌い、卯の花という別名が付けられたといわれています。卯の花という名前は白いウツギの花にたとえて付けられたようです。卯の花はさらに別名があり、それは「きらず」。卯の花は包丁を使わなくても調理ができることからこの名前が付けられたとのことで、漢字で書くと「雪花菜」となります。

おからには、食物繊維のはたらきで便秘の解消が期待できたり、食物繊維とビタミンEのはたらきで美肌効果が期待できたりと、体にやさしい食べ物です。また、かさましになり、たんぱく質も含まれるのでダイエットの方にもおすすめだそうです。
江戸中期の儒学者・荻生徂徠(おぎゅうそらい)が若い頃、あまりに貧しいため、近くの豆腐屋からおからを分けてもらい、飢えをしのいだといわれています。講談や落語の有名な演目のひとつ(「徂徠豆腐」)がそれです。また、『高野聖』で有名な泉鏡花(いずみきょうか)も、貧乏時代にはおからで食いつないでいたという逸話もあります。
首相以外の閣僚は布マスク使っていない。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 04月4日 - 日常
今日は24節気のひとつ「清明(せいめい)」で、春分から数えて15日目です。
春先の清らかで生き生きとした様子を表した「清浄明潔」という語を略したもので、万物が若返り、清々しく明るく美しい季節です。この頃はまさに桜の花が咲きほこり、お花見のシーズンでもありますね。南の地方ではつばめが渡って来る頃でもあり、雨が多い時季で、暖かくなった後に小雨が降り続いて寒くなったりもします。

沖縄では「清明祭(シーミー)」といって、墓前に親族が集まり、酒・茶・お重を供えた後、皆でご馳走をいただく習慣があるそうです。清明祭は中国から伝わったとされ、「清明の節」の期間に先祖のお墓に親戚が集まり、お線香やお花、重箱につめた料理をお供えし供養します。基本的には清明の入りから15日以内に行うのが基本だそうですが、現代では休日に行うことが多ようです。沖縄のお墓の前は「清明祭」をするための広いスペースがちゃんと設けてあります。ここで、お重を囲んで宴が催されます。気候もいい頃ですし、今ではピクニック感覚でどのお墓もとても賑やかだそうですが、ことしはコロナウイルスのせいで、どうなされているのでしょう。
コロナ感染、世界で100万人超、国内で3千人超。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 04月3日 - 日常
「花七日(はななぬか)」という言葉がありますが、桜は咲いてから散るまでが7日間に過ぎないということで、盛りの短くはかないことのたとえです。

桜の開花情報が話題となる季節になりました。まず山桜が開き始め、その後に里の桜が開き始め、今はそろそろ里の桜が咲く時期になりました。桜は種類やそれが生えている場所によって違いはありますが、開花からおよそ 7日ほどで満開を迎えるそうです。満開を迎えた桜は後は散るばかり。その盛りの短さから生まれた言葉が、今日取り上げた「花七日」です。花一時(はないっとき)とも言います。美しい桜の盛りがわずかに7日というのは何とも惜しいけれども、もし桜が7日で散る花でなくて、1年中咲き続けている花だとしたら、花と言えば桜と言うほど、愛された花となったかどうか。少なくとも今ほどみんなが桜に注意を向ける事は無かったでしょうね。
コロナウイルス騒ぎがなかったら、近郊のサクラ散策に伺いたいのですが、今年は何もかもが自粛とあらばまことに残念ですね。
福島市の小中、6日から午前中のみ授業。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 04月2日 - 日常
「ポジティブ」と言えば、人間の性格や言動を表す言葉として主に浸透しており、「性格がポジティブ」と言えば「性格が前向き」「性格が明るい」「プラス思考の持ち主」の様な意味合いが含まれています。他に、ポジティブという単語には「陽性の~」という意味が含まれていて、それが電極の陽であったり、医学用語の陽性であったり、様々な使い方をされているようです。
新型コロナウイルスのニュースで繰り返し使われている「検査の結果、陽性反応が出た」「検査の結果は陰性だった」という表現は、日本語を英語に直訳しようとすると悩んでしまいそうですが、これらは英語で、
陽性の:positive
陰性の:negative と表します。
「ポジティブ」というと何だか良いニュアンスを感じますが、病気などの検査結果を表す “positive” は「陽性の」なので、その病気にかかっているということになります。
逆に「ネガティブ」にはいいイメージがあまりないですが、検査結果では「陰性の」を表すので、その病気にはかかっていません。
もちろん病気だけではなく、妊娠検査薬や薬物検査などの「陽性/陰性」も “positive/negative” で表すそうです。言葉の使い方、用語の意味、難しいですね。

政府マスク2枚配布に賛否両論。
投稿記事を読む -
2020年 04月1日 - 日常
新年度スタートの今日4月1日は、前線を伴った低気圧が本州の南岸を進んだため、福島では朝から雨が降っていて、一時は本降りとなりました。4月の和名は「卯月(うづき)」です。卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したもの、あるいは十二支の4番目が卯(うさぎ)なので
「卯月」いわれるようになったという説もあります。

新年度に入り「心機一転」といきたいところですが、やはり今年の場合は、新型コロナウイルスの影響は甚大です。それでも、ポジティブな動きが見え始めています。例えば、自粛ムードが広がっていますが、4月1日の恒例行事である、企業からの「嘘ネタ」も例年より少ない気がします。近年は「エイプリルフール」に伴い、各企業の広報部が考え抜いて作った「嘘ネタ」が朝からリリースされ、そのおもしろさが競われていました。SNSなどで反響の大きいものは、夕方や夜のニュースで取り上げられることもあります。新年度を迎えるにあたり、気持ちも新たにリフレッシュして挑みたいですよね。4月から新しい環境に身を置く人も、そうでない人も、ポジティブに輝いていきましょう!
ようやくマスク着用、首相とその周辺。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 03月31日 - 日常
今日(3月31日)は俗にいう年度末です。これは、ひとつの年度の終わりで、日本では3月末(あるいは末日の31日特定)を指す場合が多いようです。会計や学業、農産物の作付・収穫などの種々の目的から、1年をある日から次の年のある日の前日まで「年度」として区切っていますが、その末期、末日にあたる期間のことです。
日本においては、会計年度(官公庁の歳入歳出を画定する期間)や学校年度が4月1日から翌年3月31日となっているため、ある事業やサービス等の終了と開始や人事異動が年度移りに併せて行われていたり、定められた学業を終えた児童・生徒が卒業し新しく入学するものと入れ替わるといったドラマを演出する舞台となっています。 会計年度が4月~翌3月なのは日本の他、イギリス、デンマーク、カナダなどです。 アメリカ合衆国は10月~翌年9月、中華人民共和国は暦年と同じ1月~同年12月であり、それぞれ9月と12月の下旬が「年度末」になります。
なお、学校年度ではアメリカやヨーロッパ諸国は9月~翌年8月の期間となるため、卒業式は6月頃になったりしています。

法華坊主の年度末の思い出は、1981(昭和56)年3月31日、人気アイドルのピンク・レディーが東京・後楽園球場で「さよならコンサート」を開いた日です。ミーとケイは会場を埋めたファンに5年間の応援を感謝し、ヒット曲「ペッパー警部」「ウォンテッド」「UFO」などの25曲を熱唱し、「燃え尽きました」と抱き合って泣いたシーンは今も忘れられません。しかし、当日はみぞれ交じりの冷雨が降り続く悪天候であり、主催者発表3万人とはいえ、 空席が目立ったスタンド(消防庁発表1万5000人)に象徴されるように絶頂期の面影はほとんど無く、何かと比較されたキャンディーズの解散コンサート(1978年4月)が超満員だったのと比べると、あまりにも寂し過ぎるものでありました。
コロナ、福島でも3例目4例目の感染。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 03月30日 - 日常
森喜朗東京オリンピック大会組織委会長が危ういと思いませんか? 20日の聖火引き継ぎ式に日本語でビデオメッセージを寄せた森委員長が、痛恨の言い間違えをしています。野村忠宏さんと吉田沙保里さんが日本で聖火を受け取った場所は「宮城県航空自衛隊松島基地」でしたが、「宮崎県松島空港」と紹介するなどお粗末な話です。

今日(30日)開かれた東京2020組織委員会理事会の冒頭、森喜朗会長はあいさつの中で、新型コロナウイルスの影響を考慮して19日のギリシャでの聖火引き継ぎへ日本側代表団派遣を見送ったことに関して言及しました。「聖火を取りに行けなかったのは非常に残念だったが、正直申し上げて、聖火さえ日本に取ってしまえば、という一念だった」との思いを吐露したそうです。加えて、安倍首相の提案で、当面は福島県に保管する予定の聖火について「当面は福岡県に置きましょう、ということになった」と言い間違える場面もありました。細かいことかもしれませんが、「宮城県と宮崎県」「福島県と福岡県」、大会組織委員会のトップなら間違えてはいけないところでしょう。
品格がないリーダーは、自分のことでいっぱいで頭も忙しいので、自身の地位の確保に必死だったり、地位を獲得できたことに酔いしれていることが多くあります。全体を見るという視点が欠けているために、活かすという発想はありません。活かすとは、コントロールされている自分自身に気づくことでもあります。気づかないと、そのままコントロールされた偽物の品格を身に付けて、本音では心が苦しいはずです。も安倍総理も森委員長も既存の地位にしがみつかないで、活気ある若いリーダーにその座を譲り、1年延期になったオリンピックを陰ながら支えるくらいの度量があってもよろしいと思うのは、法華坊主ばかりでしょうか。
新型コロナ感染で、志村けんさん亡くなる。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -
2020年 03月29日 - 日常
コロナパニックの時に不謹慎と言われそうですが、先月中頃に乃木坂の国立新美術館で観た「日本・ハンガリー外交関係開設150周年記念 ブダペスト国立西洋美術館 & ハンガリー・ナショナル・ギャラリー所蔵 ブダペスト―ヨーロッパとハンガリーの美術400年」展について、記録として綴っておきます。
この美術展は、ブダペスト国立西洋美術館 & ハンガリー・ナショナル・ギャラリーをはじめとする関係各位の理解と協力を得て、会期を今日3月29日まで延長していましたが、 政府から新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のための要請を受けて、途中から臨時休館を延長することとなり、そのまま閉幕となってしまった展覧会です。
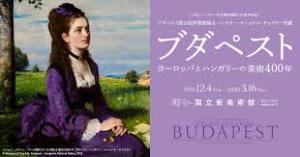
日本とハンガリーの外交関係開設150周年を記念し、ハンガリー最大の美術館であるブダペスト国立西洋美術館とハンガリー・ナショナル・ギャラリーのコレクション展は、両館の所蔵品がまとまった形で来日するのは実に25年ぶりだそうです。
ルネサンスから20世紀初頭まで、約400年にわたるヨーロッパとハンガリーの絵画、素描、彫刻の名品130点が一堂に会した本展は、クラーナハ、ティツィアーノ、エル・グレコ、ルノワール、モネなど巨匠たちの作品に加えて、日本では目にする機会の少ない19・20世紀ハンガリーの作家たちの名作も、多数出品されていました。「ドナウの真珠」と称えられるハンガリーの首都・ブダペストから一挙来日する珠玉の作品群は、一見の価値がありました。
今回の主催者は、「再開を楽しみにしてくださっていた皆様には、ご期待に添うことができずに申し訳ありません 」と広報していますが、他にも多くの美術展や催事が中止や閉幕になってしまいザンネンでなりません。コロナウイルス感染拡大が一日も早く収束し、さらには完全に終息することを願ってやみません。
関東甲信の広い範囲で季節外れの積雪。 法華坊主 joe
投稿記事を読む -